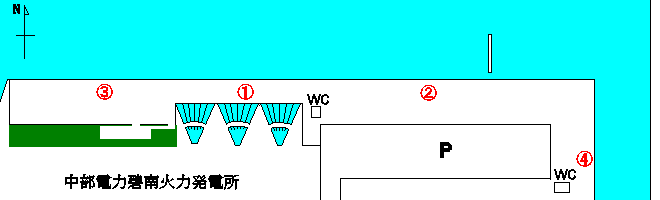
碧南つり広場
ここは、私が最も頻繁に訪れる釣り場である。広大な無料駐車場、トイレ、電話ボックス、公園などが完備している。1年中何かが釣れる。この広場の西側の一部に、中部電力碧南火力発電所の温排水口があり、ここが晩秋から初冬にかけてのクロダイ、マダカ、メッキの好ポイントになる。
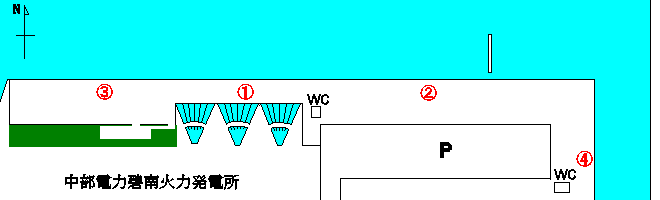
| 主な釣魚 |
 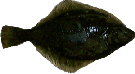 |
| ①温排水口 | |
写真1 |
つり広場で最も人気の高いポイントである。写真左手の柵の中が温排水の流れている水路である。左手から中央の道路下のトンネルを通って右手の海側へ流れている。この温排水の影響で秋から冬にかけてこの付近に魚が集まってくる。当然、釣り人もここに集中して混雑する。 写真を見て分かるように、殆どの釣り人は柵の方に集まっている。柵の間から竿を通して排水溝の中へ仕掛けを投入して、クロダイとマダカを狙っている。海側でも釣れないことはないのだが、寒い時期は排水溝の中のほうが確率が高い。写真は6月に撮ったのだが、この時期でも排水溝の中ではクロダイが釣れていた。 1年中何かが釣れるが、最もよい時期は晩秋から初冬にかけて(11月、12月)である。この時期、主に釣れるのはチンタ、クロダイ、セイゴ、マダカ、メッキである。ワタリガニも多い。また、投げ釣りで落ちハゼ、カレイ、アナゴも釣れる。逆に最も釣れない時期は2月、3月である。この時期はボラの大群で埋め尽くされ、ボラ以外に大きい魚は殆ど釣れない。ただ、昼間は小型のコノシロ(コハダ)や稚アユなど小魚が釣れる。 |
| ②駐車場北側 | |
写真2 |
写真でも分かるとおり温排水口よりも広くて釣りやすい。ただ、すぐ西側に温排水口があるため、水温が低くなる時期には、どうしても魚が温排水口付近に集まってしまう。そして、この場所はあまり釣れなくなり、釣り人も少なくなる。しかし、初夏から秋にかけては、ここも釣り人で賑わう。場所が広く、駐車場やトイレも近いのでファミリーフィッシングには最適である。イス、テーブル、パラソル持参でお弁当を食べながら釣りをしたり、バーベキューをやりながら釣りをしている家族も居る。 春は数は少ないがメバル、夏はセイゴ、ハゼ、サッパ、ゼンメ、ギマ、秋はセイゴ、サヨリ、ハゼ、カレイなどが釣れる。冬でも投げ釣りならば落ちハゼやカレイが釣れる。 |
| ③温排水口より西側 | |
写真3 |
温排水口よりも西側の一帯である。ここも温排水口前より広い。小さな公園もあり、家族連れにはよさそうだが、トイレから遠いのが難点である。釣れる魚は駐車場北側と同様である。 |
| ④駐車場東側 | |
写真4 |
広々とした芝生の公園があり、家族連れでのんびりと釣りができそうだが、釣り人は少ない。あまり釣れないようだ。以前、夏の夜釣りで何度か通ったことがあるが、小さなハゼしか釣れなかった。前の水路はかなり深くて釣れそうに思えるのだが、釣り人は殆ど居なくて、時折1人か2人居るくらいだった。ただ、水路を挟んで対岸はクロダイ、キビレの落とし込み釣りの実績場らしく、昼間は落とし込み釣りをやっている人をよく見かける。 |
碧南つり広場と言えば温排水溝である。この温排水溝についてもう少し詳しく説明しよう。
ここは発電所の温排水が流れているため、周辺に比べて水温が高く、水温の低い時期に魚が集まってくる。夏場は特別よいポイントではないが、秋になり水温が下がるにしたがって次第に有利なポイントになっていく。10月初旬までは排水溝の中ではあまり釣れない(釣っている人が少ない)が、外側ではセイゴがよく釣れる。10月中旬頃から排水溝の中でチンタ(クロダイ)、セイゴ(マダカ)が釣れ始める。そして、最盛期の11月、12月を迎える。この時期にはメッキも次第に排水溝の中へ入って来る。
排水溝での釣りは非常にやりにくい。写真5のように高さ2mほどの柵があり、柵の間から竿を通して釣りをしなければならない。多くの人は竿掛けを柵に固定してそこへ竿を掛けている。魚の取り込みもやりにくい。大きい魚の場合、タモを柵の間から通して取り込まなければならない。小さい魚の場合、釣り上げたら柵の間から手を伸ばして魚を掴まなければならない。そんなに釣りにくいのだが、シーズンになると大物が釣れるので大勢の釣り人で超満員になる。狙いはクロダイ、マダカ、メッキと様々である。
写真5 |
排水溝は3つあり、東側から1号機、2号機、3号機と呼ばれている。これは3つの発電機に合わせてこう呼ばれているようである。それぞれの排水溝は写真6で分かるように6つの水路に分割されて、それぞれ東側から順に1番、2番、3番、・・・と呼ばれている。そして、1号機の3番であれば「1の3」、3号機の6番であれば「3の6」というように呼ばれている。1,2,3号機共に1番、2番は流れが遅く、4番から6番は速い。3番は右端と左端で速さがかなり違う。右端は遅く、左端は速い。また、1番の水路は非常に浅い。
写真6 |