| 図1 衣浦湾最奥部 | ||
| (a) 現在(2000年頃)の衣浦湾最奥部 | (b) 元禄時代(1688年〜1704年)の衣浦湾最奥部の想像図 | |
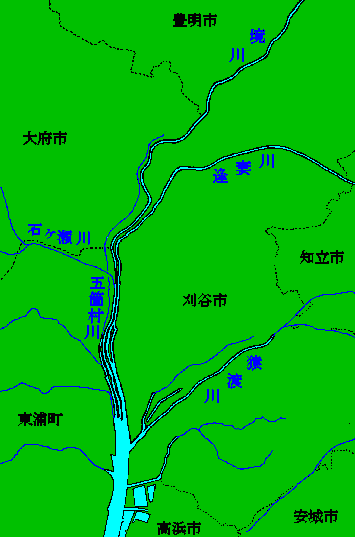 |
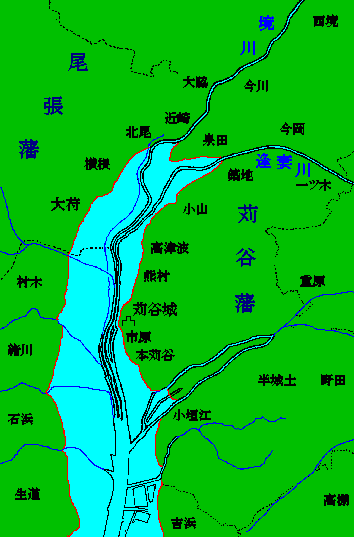 |
衣浦湾の歴史
江戸時代
この時代は全国各地の沿岸同様、衣ヶ浦も新田開発のための干拓が盛んに行なわれた時代である。干拓によって海岸線は大きく変化した。陸地が増え、衣ヶ浦は狭くなり、湾の奥は川になった。干拓による新田の増加で米の収穫が若干増えたが、良いことばかりではなかった。これら干拓地は度々水害に見舞われ、その度に大きな被害を出した。干拓は、埋立のように海に土砂を入れて陸地を作るわけではない。干潟を堤防で囲んで、干潮時に水門を開けて排水し、排水したら水門を閉じて満潮時は海水が中に入らないようにするだけである。したがって、干拓地は海抜ゼロメートル或いはゼロメートル以下のところが多い。つまり、満潮時には水面より低い土地である。堤防が決壊すると、たちまち海水が流れ込んで元の海に戻ってしまうのである。現代のように強固なコンクリートの堤防が無かった江戸時代は、これら干拓地は堤防の決壊で度々海水に浸かっている。江戸時代以降でも、現在のような強固な堤防が築かれる以前は度々水害に見舞われた。昭和34年(1959年)の伊勢湾台風では、これら干拓地が空前の大被害を被った。衣ヶ浦の干拓地も堤防が決壊して水に浸かり、昔の衣ヶ浦を再現したような光景であったという。
それでは、何をきっかけに干拓が始まり、どのように陸地が広がっていったのか見てみよう。
【衣ヶ浦最奥部】
衣ヶ浦最奥部の刈谷市と大府市、東浦町の間に挟まれた一帯はかつて海であった。現在、この辺りは逢妻川(あいづまがわ)、境川、五箇村川が並んで南の下流部で合流している(図1(a)参照)。しかし、江戸時代末期まではこの辺り一帯は海であった。図2を参照されたい。これは稲垣氏時代(1651年〜1702年)の刈谷城図である。図の上側が西である。図の左上に「入海」という文字がある(図をクリックすると大きな図を見ることができる)。つまり海である。この城は現在の刈谷市亀城(きじょう)公園の場所にあったので、亀城公園の西側はすぐ海だったのである。図3は現在の亀城公園西側の写真である。図2の一番上の城の本丸西側の土手付近の位置から撮った写真である。図3の写真の左手には、写っていないが本丸西側の崖がある。写真の駐車場や向こう側に見える高圧線の鉄塔や建物のある場所は昔は海の上である。
かつて、この辺りは衣ヶ浦最奥部の入り海(入り江)であった。図1(b)を参照されたい。入り海は泉田村(現刈谷市泉田町)の辺りまで入り込んでいた。入り海の幅は平均でもおよそ1.5km程あったと思われる。この幅は現在の衣浦湾の碧南市南部と武豊町の間の幅に匹敵する。現在の刈谷市と東浦町の間の川幅は最も広い部分でも300m程しかなく、かつてそんなに広い入り海だったことなど今の我々には想像もつかない。この入り海と境川を境界にして東が苅谷藩、西が尾張藩であった。
図1 衣浦湾最奥部 (a) 現在(2000年頃)の衣浦湾最奥部 (b) 元禄時代(1688年〜1704年)の衣浦湾最奥部の想像図
図2 刈谷城図 図3 亀城公園西から南方向を写した写真(2001年2月)
このような入り海であれば当然船を利用した海上交通は盛んであった。その頃は各所に船で荷を積み出したり、荷揚げを行なったりする「土場」と呼ばれる場所があった。刈谷市では泉田村土場、市原土場、小垣江土場(半崎土場、清水土場)、下重原土場(三ツ又土場)、小山村下土場、中手土場などが知られている。また、各所に対岸の村への渡し場があった。刈谷城のすぐ南の市原(いちばら)と対岸の緒川村との間には海上15町(約1.6km)の渡しがあった。渡し賃が六文であったため「六文の渡し」と呼ばれた。さらに、熊村と村木村の間には海上11町30間(約1.2km)、高津波村と大府村の間には海上12町20間(約1.3km)、小山村と横根村の間には海上13町20間(約1.4km)の渡しがあった。
| 図4.半崎土場跡(猿渡川下流の巡見橋付近) |
また、この入り海では漁業も盛んであった。沿岸の村々には漁師がいて漁を行なっていた。当時、刈谷藩は衣ヶ浦で獲れる白魚(シラウオ) を干して目刺にして幕府に献上していた。この白魚は本苅谷村、市原町、高津波村の漁師が捕り、藩に納めていた。尾張藩では石浜村、緒川村、生道(いくじ)村が白魚漁を行なっていた。弘化3年(1846年)には石浜村漁師が尾張藩主への献上を認められ、後に緒川村、生道村も認められている。また、白魚の他に緒川海老と呼ばれる小海老が緒川村、石浜村で獲られ、干して売られていた。
当時の衣ヶ浦には塩田があり、製塩が行なわれていた。衣ヶ浦での製塩の歴史はかなり古く、古代古墳時代から行なわれていた。江戸時代に入っても製塩は続いており、生道村の南に位置する藤江村では明治33年まで続いている。製塩が行なわれていた村は尾張藩側では村木村、緒川村、石浜村、生道村、藤江村であり、苅谷藩側では高津波村、本苅谷村、小垣江村である。江戸時代、製塩の行なわれていた村々の年貢の一部は塩年貢であった。苅谷藩では、小垣江村、本苅谷村が塩年貢を納めていた記録が残っている。
このような海と関わる生活も江戸末期になると次第に消えていくことになる。そのきっかけは境川の土砂の堆積で入り海が次第に浅くなってきたことである.そして、新田開発のため尾張藩側、苅谷藩側ともに干拓が行なわれ、入り海の幅が次第に狭くなり、さらに、苅谷藩側の新田の水害対策として陸地側の逢妻川筋を境川筋と別水とするため長い堤を築いた。こうして次第に現在の川のようになっていった。
江戸時代の初期、境川は東海道の御境川橋まで舟が出入りできた。しかし、土砂の堆積が激しく次第に浅くなってきた。土砂は境川の運ぶ土砂だけでなく、西の尾張、東の三河から境川、逢妻川、衣ヶ浦に注ぐ中小の河川からも運ばれた。衣ヶ浦最奥部のこの辺りは西の尾張側は丘陵地帯が多く、全体に土地が高いのに比べ、東の三河側は平地で尾張側に比べて土地が低い、そのためか尾張と三河の境を流れる境川の方が三河を流れる逢妻川よりも土砂の堆積が激しかった。このため、境川の川底は次第に逢妻川の川底より高くなり、洪水のときは境川から逢妻川へ水が逆流するようになった。 土砂の堆積がこの土砂の堆積作用で干潟が広がり、その干潟を干拓し始めた。
| 図5.境川筋と逢妻川筋を別水とするために築かれた堤防 |
 |
【北浦】
北浦という入り江をご存知だろうか。今はもう消え去った入り江で、安城市と碧南市の境に油ヶ淵として僅かにその痕跡だけを残している(図1(a)参照)。江戸時代初期まで、この油ヶ淵一帯は北浦と呼ばれる入り江であった。図1(b)を見ていただきたい、北浦は衣ヶ浦のすぐ東側に位置した入り江で、今の碧南市鷲塚は島であった。そして、今の安城市の城ヶ入、根崎、東端、和泉は海に面した村だった。これがなぜ湖沼になってしまったのか。それは、矢作川の流れを人為的に変えたことで、川によって運ばれた土砂が砂州を形成し入り江の一部を埋めてしまい、さらに、砂州や浅瀬が広がり、それを利用して新田開発が行なわれたためある。
かつて、矢作川はもっと南の一色と吉良の境に河口があり、三河湾に注いでいた。今の矢作古川がそれである。このかつての矢作川は度々水害をもたらしていた。そこで、西尾城主本多康俊は幕府の命により桜井村(現安城市)の木戸から米津の間に矢作新川を掘って、矢作川本流を北浦へ落とした。1605年のことである。ところが、この矢作新川は勾配が急であったため大量の土砂を運び、入り江をどんどん埋めていき、10年ほどで米津から鷲塚まで砂州でつながってしまった。そして、1644年には幕府が米津から鷲塚まで堤防を築き、北浦は完全に海から切り離された。これが今の油ヶ淵になったのである。
図1 衣ヶ浦東岸と油ヶ淵周辺 (a) 現在(2000年頃)の油ヶ淵とその周辺 (b) 1600年頃の北浦とその周辺の想像図 (c) 上図(a)、(b)の示す位置と範囲
海から切り離され閉鎖された湖沼となった油ヶ淵(北浦)には周辺の河川から流れ込む水が排水されずに沿岸の村は水害を蒙ることになった。そこで、東浦へ向けて排水路が作られ、これによって油ヶ淵の水が排水できるようになった。その後、油ヶ淵沿岸には干拓によって新田が築かれていった。しかし、年数が経つと東浦には矢作川によって運ばれた土砂がさらに堆積して排水が悪くなり、油ヶ淵沿岸の村々は再び水害が増えた。そこで、鷲塚村の西から平七村の東にかけて新たに排水路を堀り、これによってしばらくは排水もよくなった。そして、再び新たな新田が作られていった。しかし、貞享年間(1684〜88)頃から再び矢作川の土砂が堆積し排水が悪くなり、油ヶ淵沿岸は水害が増加した。そのため、新たな排水路として宝永2年(1705)に新川を掘ったが、それも十分ではなく、昭和10年(1835)に高浜川が開削されてようやく排水問題は解決した。もともと水害対策として矢作川の流れを変えたのだが、その影響で別の場所が水害を蒙ることになり、その後数百年もその対策に追われることになってしまった。しかし、悪いことばかりではなかった。矢作川の運んだ土砂によって入り江に砂州や浅瀬が多くできたことによって干拓が可能になり、そこに新田を築くことができた。この辺りを領有していた藩にとっては石高が増えるので歓迎すべきことであったろう。
今の油ヶ淵はもともと衣ヶ浦の入り江だった名残りで今でも塩分を含む汽水湖である。下層の水は上層に比べ塩分を多く含んでいる。
| 図2.現在の油ヶ淵(2001年7月) |
 |
参考資料
・「シリーズ愛知1 碧海の歴史」 村瀬正章著 松籟社
・「江戸時代 人作り風土記 23 愛知」 農山漁村文化協会
・「刈谷市史 第二巻 近世」
・「安城市史」
・「大府市誌」
・「東浦町誌 本文編」
・碧南市ホームページ 〜 碧南事典